 (※イメージ画像となります)
(※イメージ画像となります)
「保険に入ったのがいつか覚えていない」という方は意外と多いものです。人生の節目を迎えるたびに、生活スタイルや収入・支出は変わりますが、保険だけが“過去のまま”になっているケースも少なくありません。見直しはお金を減らすためではなく、“いざというときの備え”を今の自分に合わせる作業です。大切なのは難しい専門知識ではなく、「今の暮らしに合っているか」を冷静に見つめ直すことから始めることです。
小話:引っ越しで気づいた「保険の置き去り」
先日、引っ越しの片づけをしていたときに、10年前の保険証券が出てきました。引っ越し先の間取りも、家族の人数も、収入もすっかり変わっているのに、保険の内容は当時のまま。「あれ?今この保障、必要なのかな」と考え始めたのがきっかけでした。結果、不要な特約を外して月3,000円ほど固定費が軽くなり、逆に就業不能保障を追加。保険料は変わらないのに、内容はぐっと現実的に。片づけって、保険の“棚卸し”にもつながるんだなと感じた瞬間でした。
ステップ1:まず「今の生活」を数字で見える化
見直しの最初は、家計簿を完璧にする必要はありません。ざっくりで構わないので、「住居・食費・教育・医療」など、毎月の支出の中で変動しにくい項目を整理しましょう。特に、今後3〜5年の間に起こりそうなライフイベント(出産、住宅購入、転職など)をざっくり書き出すと、どんなリスクに備えるべきかが見えてきます。保険の話は「過去」ではなく「これから」を軸に考えるのがコツです。
ステップ2:保険を役割ごとに分けて考える
保険を見直すときは、「何を守るのか」で分類するのがおすすめです。
・死亡保障:家族の生活維持
・医療保障:病気・けがの出費対策
・就業不能保障:働けなくなったときの生活費
この3つを分けて考えると、重複や不足がわかりやすくなります。たとえば、住宅ローンに団体信用保険がついていれば、死亡保障を減らしてもよい場合もあります。逆に、フリーランスや個人事業主なら就業不能保障を厚くするほうが現実的です。
ステップ3:固定費としての上限を決める
保険料は「払える範囲」で設計することが大切です。目安として、月収の5〜10%以内に保険料を収めると無理がありません。見直しの目的は「節約」ではなく「持続可能な備え」をつくること。今は余裕があっても、将来の支出が増えるタイミング(教育費、住宅ローンなど)を想定して、固定費を抑えることが将来の安心につながります。
ステップ4:比較は“金額”より“使いやすさ”で
同じように見える保険でも、いざというときに「手続きが面倒」「どこに連絡すればいいかわからない」といった違いが出ます。見直し時には、給付請求の方法や解約・特約の変更がしやすいかなど、“使いやすさ”の視点で比較しましょう。3社くらいの見積もりを並べ、メリット・デメリットを自分の言葉でメモしておくと次の見直しが楽になります。
ステップ5:家族で共有し、“更新日”をカレンダーに
どんなに良い保険でも、家族が内容を知らなければ意味がありません。保険の見直し後は、契約内容を1枚にまとめ、スマホのカレンダーに更新日を入れておくのがおすすめです。契約一覧を家族で共有しておくだけで、いざという時の動きが変わります。見直しは“安心を家族で持てる状態”にすることがゴールです。
 (※イメージ画像となります)
(※イメージ画像となります)
まとめ
保険の見直しは、「削る作業」ではなく「整える作業」です。生活の変化に合わせて、いま必要な備えを確認し、重なりや抜けを調整すれば、それだけで家計は安定します。年1回、誕生日月などに点検日を決めておくと、無理なく続けられます。未来の安心は、今日30分の整理から生まれます。
「見直しってなんだか難しそう…」と感じたら、保険証券を一枚だけ取り出して“タイトルだけ眺める”ところから始めてみてください。意味がわからなくてもOK。次にプロに相談する時に「この書類、なんですか?」と聞けるだけで十分です。あとは、お気に入りのカフェでコーヒーを飲みながら、「来年もこのくらいの安心でいいかな」と考える。保険の見直しは、肩の力を抜いてちょうどいいくらいがベストです。

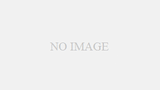
コメント