 (※イメージ画像)
(※イメージ画像)
会社経営を突き詰めると、「とにかく売上をあげる」と「自分の分身をつくる」の二つに行き着きます。最初は利益を厚くし、時給単価を押し上げ、新たな収益導線を生み出すことに集中する。やがて個人の限界(いわゆる“2億の壁”)が見えたら、分身化と標準化で組織に拡張する段階へ。この記事では、2段階を実務レベルの手順に落とし込み、明日から動ける一歩を提示します。
会社経営は突き詰めると、この二つに集約されます。
〈1〉とにかく売上をあげる。
〈2〉自分の分身をつくる。
まずは順番が大事です。最初から仕組み化や採用、教育に気を取られると、肝心のキャッシュが細り、意思決定の自由度が失われます。最初のフェーズは、いまのビジネスをもっと儲かる構造に磨き込むことに集中しましょう。
〈1〉とにかく売上をあげる—“時給単価”を押し上げる
この段階で見るべき指標はシンプルです。
自分の時給単価を最大化できているか
新たなお金の流れ(新商品・新チャネル・価格改定・客層転換)を生み出せているか
人を雇ってでも回す価値がある粗利の厚みがあるか
たとえば、同じ1時間でも「提案の質」を上げるだけで受注単価は変わります。価格を上げる根拠を言語化し、オプション設計でLTVを伸ばす。集客チャネルは一極集中を避け、既存顧客の紹介導線を標準装備にする。“回る仕組み”は後でよい、まず“回る数字”を作る。 これが鉄則です。
このフェーズの目安として、個人で到達しうる売上の上限は概ね2億円と言われます。もちろん業種によって上下しますが、限界効用が逓減するのは共通です。ここまで来たら、次の壁—組織化—に移行する合図です。
〈2〉自分の分身をつくる—スケールのスイッチを入れる
次のステップは、“自分”というボトルネックを外すこと。
社長1人がフル稼働しても、売上の伸びは頭打ちになります。そこで考え方を切り替えます。
社長の分身を1人つくる。
その分身を5人に増やす。
ここで重要なのは「完全コピーではなく、社長の実力の3分の1を目安にする」こと。3分の1でも、5人集まれば社長1.67人分の生産力になります。プロセスの標準化、提案資料の型化、意思決定基準の明文化、これらを“持ち運べる知”に変換します。
100億企業の共通項—“三分の一×人数”の発想
私がご支援する中で印象的だったのが、100億企業の創業者の言葉です。
「本部長クラスや子会社役員が50人いる。平均で社長の3分の1の力がある。つまり“社長15人分”だ。社長1人で10億は簡単。10億×15人=150億は現実的だ。」
極端に聞こえるかもしれませんが、ロジックは明快です。“代替可能な強さ”を標準装備にし、それを人数で増幅させる。 2億→10億、10億→20億の伸長は、この延長線上にあります。
分身づくりの実務:5つのレバー
言語化:勝ち筋(ターゲット・提供価値・価格根拠)を1枚に落とす
型化:提案書・見積・議事録・KPIシートをテンプレ化
計測:ファネルごとに“次に直す場所”が自動で光るダッシュボード
伴走:OJTは“見る・やる・教える”の3サイクルを週次で回す
権限移譲:金額・割引・採用の稟議基準を数値で明確化
この5つを回すことで、3分の1の分身が現実味を帯びます。最初の分身づくりが一番重い。だからこそ、一人目に全精力を投下してマニュアルと教材を仕上げると、その後の採用・教育コストが指数関数的に下がります。
ありがちな壁と処方箋
「自分がやった方が早い」病
→ “二度目以降は他人が30分で再現できる資料”を作るまでがあなたの仕事。
品質のバラツキ
→ “合格/不合格ラインの具体例”をライブラリ化。OK・NGの境界を見せる。
採用ミスマッチ
→ スキルより“学習速度”に投資。試用期間の学習KPIを設定する。
権限委譲の不安
→ “逸脱コスト<ボトルネックコスト”。限度額と裁量範囲を数字で管理。
個人事業主と経営者の分岐点
**壁を越える鍵は「分身化」**にあります。個人で稼ぐ力は尊い。しかし、事業を資産化するためには、人と仕組みに価値を移す必要がある。年商や規模に関係なく、どの段階でも通用する原理原則です。
 (※イメージ画像)
(※イメージ画像)
まとめ—今日からできる一歩
まずは時給単価を上げる施策を一つ、今日決める(値付け見直し、オプション化)
次に最重要プロセスを録画/記録し、手順書とチェックリスト化
一人目の分身育成に全投資。教材は“次の5人”前提で作る
売上を上げる→分身をつくる。
この順序を守るだけで、伸び方は一変します。経営の本質をもう一度見直し、次の壁を越えていきましょう。

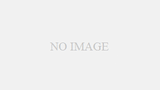
コメント