 (※イメージ画像となります)
(※イメージ画像となります)
「今の仕事を続けていいのか、でも辞めるのも怖い」——この迷いは多くの人が通る道です。
情報過多の時代、SNSで他人の成功を見て焦り、自分を見失う人が増えています。そんなとき必要なのは“正解”ではなく“軸”。キャリアコーチングは、その軸を一緒に見つけるための伴走支援です。人事歴20年の私が実感するのは、キャリア迷子の9割が「自分を知らないこと」が原因だということ。今回は、キャリアコーチングの重要性を、現場目線で紐解いていきます。
焦る若手と「未来の焦点」
5年前のある面談で、入社3年目の若手が言いました。
「僕、周りの同期がどんどん昇進してて、焦ります」。
私は聞き返しました。「じゃあ、君の目標は?」
彼は沈黙しました。焦りの正体は“比較”であり、“目的の欠如”です。
キャリアコーチングでは、この「焦りの構造」を分解します。
未来を考えるとき、人は“他人の速度”に影響を受けがち。
でも、必要なのは“自分の地図”を描くこと。
私がその若手に伝えたのは、「焦りは悪くない。ただ、焦点を他人から自分に戻そう」ということ。
半年後、彼は部署異動を自ら提案し、今はプロジェクトリーダーです。
人は“焦り”を敵にするか、“行動の燃料”にするかで、人生が変わります。
「自己理解」がすべての出発点
キャリアコーチングが重要なのは、スキルや転職ノウハウよりも「自己理解」を深める場だからです。「何が得意か」「何が嫌いか」を言語化できる人ほど、キャリアの選択肢を誤りません。
逆に、自己理解が浅いまま転職すると、職場を変えても同じ悩みが再発します。
人事として多くの退職面談に立ち会ってきましたが、その多くは「やりたい仕事じゃなかった」という言葉でした。キャリアコーチングは、その前に立ち止まり、「自分の中に答えを見つける練習」をする場所なのです。
「視点の転換」が生む変化
コーチングの効果は、“視点が増える”ことです。
例えば、「会社が悪い」ではなく、「自分がどう関わるか」に意識が変わる。
これは単なる思考術ではなく、“自己責任の拡張”です。
自分の行動範囲が広がると、人間関係も成果も変わります。
キャリアとは環境の問題ではなく、解釈の問題。
同じ状況でも「チャンス」と感じる人と「限界」と感じる人の差は、この視点の転換力にあります。
コーチングはまさにその“見方の筋肉”を鍛える場所です。
「感情整理」が決断をクリアにする
多くの人がキャリアに悩む理由は、情報ではなく感情が混乱しているからです。
「上司が合わない」「評価が低い」「なんとなく疲れた」——これらはすべて感情の表面。
コーチングでは、その裏にある“本音”を言葉にしていきます。
「自分を認めてほしかった」「挑戦したかった」など、核心が見えると次の一歩が明確になります。
感情を整理することは、決断の第一歩。
頭で考えるより、“心の声”を聞く勇気がキャリアを動かすのです。
「第三者の視点」が自己成長を加速させる
自分の中で考える限界は、思考の癖にあります。
だからこそ、第三者のコーチの存在が重要です。
人は他者の問いによって、自分を“再発見”します。
「なぜそう思うのか?」と聞かれた瞬間、自分の思考の根っこを掘り起こすことになる。
その過程で「実は私、挑戦が怖かっただけだ」と気づくこともあります。
自分一人では気づけない“盲点”を照らす存在——それがコーチの役割です。
「キャリアは積み上げではなく、選び直し」
キャリアは線形ではありません。
転職や異動、ライフイベントで何度も“選び直す”ものです。
キャリアコーチングは、その選択のたびに「軸を再設定」する時間。
20代と40代では価値観が変わるのが当然です。
その都度、立ち止まり、整える——その習慣が「後悔しないキャリア」を作ります。
一度の選択で完璧を求めず、定期的にメンテナンスする発想が、これからの働き方には不可欠です。
 (※イメージ画像となります)
(※イメージ画像となります)
まとめ
キャリアコーチングの重要性は、「自分を深く知る力」を育てることにあります。
人は、環境を変えるより“解釈”を変えるほうが難しい。
でも、その一歩を踏み出せた人ほど、仕事も人生も軽やかになります。
コーチングは特別な人だけのものではなく、「真剣に生きたい人」すべての味方。
迷った時こそ、自分と対話する時間をつくってください。
それが、次のキャリアを拓く“最初の勇気”です。
ある人がコーチングを終えた後に言いました。「結局、答えは自分だったんですね」と。
私は笑って「そうですよ、コーチングは“あなた探しゲーム”です」と返しました。
正解を探す旅は終わらないけれど、自分を知る旅は確実に進む。
キャリアは迷うもの、そして迷える自分を笑えるようになった時、人は強くなります。

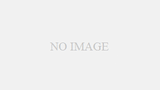
コメント